欅(ケヤキ)材は日本の高級木材の代表格として、古くから様々な建築物で使用されてきました。「見た目の美しさ」「力強い木目」「加工の難しさ」という三位一体の個性を持つ、まさに建築部材として“生きた素材”です。選ぶ際は、自分がどんな空間や用途に使いたいかをイメージしながら、これらの着眼点をじっくり見極めるのがポイントです。
古来より、欅材は神社仏閣の主要な柱には必要不可欠な材であるとされてきました。戦国時代以降、その城や城門にも好まれて使われています。例えば、旧江戸城(現皇居)の重要文化財に指定されている「田安門」や「清水門」にも利用されています。田安門は現存する旧江戸城の遺構のうち最古のものであり、1636年に作られたものですが、未だ当時のままその姿を保っています。
このように材として非常に優秀な欅(ケヤキ)材ですが、ここでは3つ着眼点として、【木目(杢)】【色・つや】【加工性】に着目して、それぞれが欅の魅力と価値を左右する重要なポイントをご案内いたします。
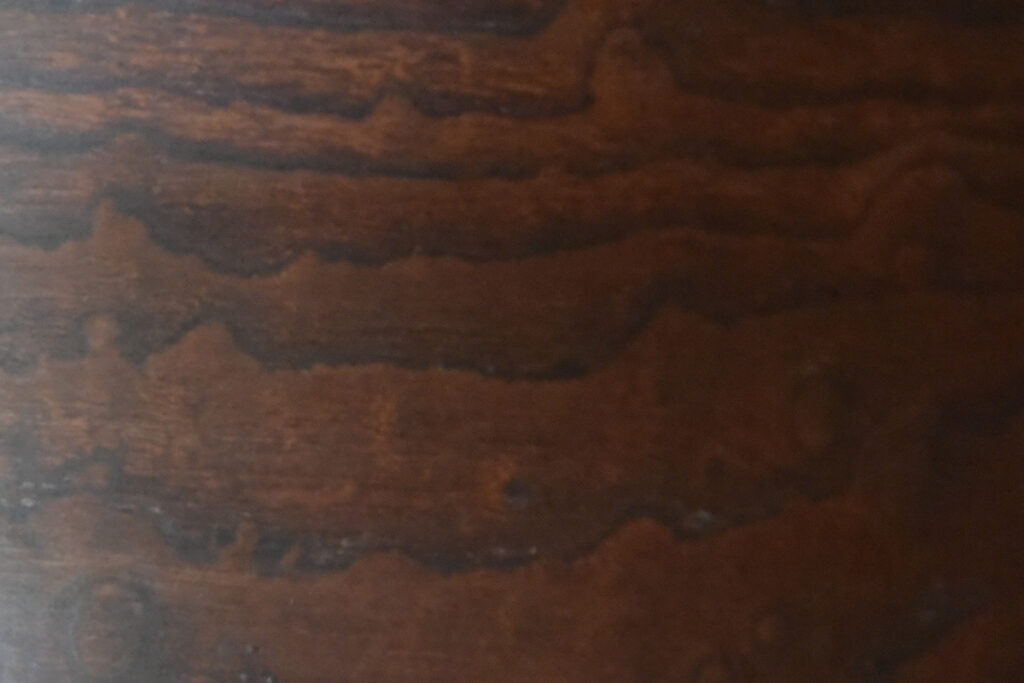


1. 木目(杢):唯一無二の表情
柾目・板目・杢目の違い。柾目はまっすぐで端正、板目は波打つような模様。瘤によって生まれる複雑な杢目。特に玉杢や如鱗杢は希少価値が高い。
2. 色・つや:視覚的な美しさと経年変化
色合いの個体差が大きいのも欅材の特徴。赤味の強い「赤ケヤキ」、白っぽい「青ケヤキ」など一本一本に違いがあります。また、経年変化が楽しめ、使用とともに色が深まり、朱色やこげ茶色に変化。木目も黒く際立ち、味わいが増します。丁寧に磨くことで自然なつやが出たり、塗り漆やウレタンなどのコーティングによるつやを出す方法もあります。
3. 加工性:扱う職人の腕が問われる
欅は非常に硬く、加工が難しく、比重は0.69(0.47-0.84)と杉の0.38(0.30-0.45)の約二倍を持ち、刃物が欠けるほどの硬さです。そのため、戦国時代には製材が不可能とされたほど。※平均値()内は最小値-最大値
また、暴れやすいという性質で、含水率の管理が難しく、乾燥が不十分だと反りや割れが生じやすく、丁寧な乾燥と加工技術が必要です。そのため、信頼できる木材業者選びが重要で、経験豊富な職人や技術力が不可欠です。



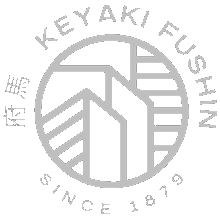
Tell us about your thoughtsWrite message