武蔵欅(ケヤキ)とは、埼玉県川越市や所沢市など武蔵野台地一帯を産地とした欅のことをいいます。大都市江戸に近く、輸送の便が良いため、江戸時代には重要な供給地となりました。代表的なものでは「川越の欅並木」があり、街道沿いや社寺の境内に大きな欅が育っていました。
武蔵欅の特徴は、目の細かさでは会津や置賜に及びませんが、素直で加工しやすい材質で建築材として扱いやすく、堅牢で耐久性が高い大径木も多く、梁・柱に好まれました。そのため、城の修復や寺社造営、町屋建築の蔵造りに用いられ、江戸に近いことから都市需要向けの安定供給に、実用銘木として重宝されたといいます。
特に川越は「小江戸」と呼ばれる城下町で、江戸との結びつきが強く、江戸城の修築や徳川家ゆかりの寺社の普請では、近郊材として「武蔵欅」が大量に伐り出され、舟運や陸路で江戸へ運ばれたといいます。地元でも川越の蔵造りの町並み(現在も残る黒漆喰の蔵)には、欅材が梁や柱に多用されています。また、街道沿いの「川越の欅並木」は江戸時代から名所として知られていました。
現在でも有名な川越の蔵造りの町並み(重要伝統的建造物群保存地区)は、江戸大火後に普及した防火構造の蔵が特徴で、その構造材に武蔵欅が大きな役割を果たしています。例えば川越最古の蔵造りである「大沢家住宅(川越市元町、江戸期建築)」は主要構造材に欅を使用しています。「中成堂歯科医院(川越市仲町、明治期建築)」も蔵造りの代表的町屋建築で、欅材の梁や柱が使われています。このように現在は観光地となっている川越の商家蔵群(仲町~幸町)多くの建物の骨組みに欅が用いられ、都市防火と商家繁栄を支えてきました。

大沢家住宅(江戸期建築)

中成堂歯科医院(明治期建築)
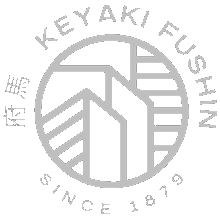
Tell us about your thoughtsWrite message